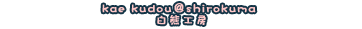25時発の列車 |
高校の同窓会は、私にはあまりにも居心地が悪いものだった。
8年たって、大学や短大、専門学校を卒業し社会人として働いている元同級生たちのきらびやかさは、目にまぶしい程だったし、既に妻や母となった元少女たちは、貫禄をみせて話しまわる。
私はイラストレーターと言えば肩書きはいい、ただのフリーターだ。彼女らには勝てそうに無い。
それに……元々男性が苦手だった私には、男性は話す対象じゃなかった。
ナツちゃんがくるから来たんだけどな。
ナツちゃんというのは、高校時代で唯一の女友達だ。美人で成績も良く、性格もさばさばしたナツちゃんは、私の憧れの対象だった。
今でもナツちゃんとは良く会うが、やはり彼女は変わっていない。堂々とした態度は、会社員になってからも変わらない。
でもナツちゃんからは、さっき「仕事が切羽詰ってこれない」というメールが来た。
「……………」
一口だけ口をつけたビールのビンを見て、私は居心地の悪いものを感じていた。
先生は仲良かったけど、皆に囲まれて話しかけられもしない。あの時、私の背を押してくれた先生。でもなんであんなに遠いんだろう……。
ぼんやりと、料理をつつきながら「来るんじゃなかった」という言葉だけが脳裏を飛来する。
いや、やっぱり帰ろう。
とん、とコップを置いて誰にも知られず席を立とう、とした時だった。
「ふーこ。どこ行くのう?」
あきらかにあざけったような声が聞こえた。
う……と私は言葉に詰まる。
それは高校時代苦手だった人で、私はあからさまに今回の席でも避けていた。それが癇に障ったのか、それとも酔っ払っているのか。薬指には燦然と輝くプラチナの指輪。どうやら開業医と結婚したと、先ほど自慢していたのを聞いた。
「あんたさぁ、おもしろい話って無いのー。というかさあ、昔からだよね。そーいうとこ。自分で逃げちゃうと事かさぁ」
「そーよねー」
周りからも同意の声。
私は体がすくんで逃げられない。何度もいじめられた恐怖心は、20歳を過ぎても超えられないもののようだった。
「アキヒコ君とか、ナツとはどうなったのよ?」
アキヒコ君というのは、唯一私と仲が良かった男子だ。いつも、ナツちゃんとアキちゃんでつるんでた。それを三角関係……いや、ナツちゃんとアキちゃんの関係に入るお邪魔虫と思われてた節があった。それが学校で私が嫌われていた一つの要因でもあった。
「あ……ナツちゃんも、アキちゃんも相変わらず元気だよ……」
「そうじゃなくてぇ」
馬鹿にした声。
「あんたお邪魔虫なんだから、さっさと身をひきなさいよね。アキヒコ君だって迷惑してるはずなんだから」
私はそれに答えられない。
「アキヒコ君とナツが結婚できないのって、あんたのせいでしょう。さっさと身を引きなさいよ」
彼女はかなり酔っ払っている。
そして、私はその質問に答えられない。答えれば彼らへの裏切りになるからだ。
「さっさと、なんか言いなさいよ。だいたいさぁ、あんたのその態度が高校から大っ嫌いだったのよね。ねえ、聞いてる?」
言葉はループしている。
周りの女子も、これはやばいかと思ったのか、彼女を止める方向に行っているが。
……もう限界だ。
鞄は向こう。それをどうにか取って、ここから去ろう。
だってもう泣きそうだ。
だん! と、ひときわ大きな音を立てて座敷の上を走る。鞄を取り靴に足をつっかけ……そこで、私の動きは止まった。
じたばたじたばた。
体が動かない。
誰かに抑えられている。
成人女性より二周りほど小さな身体の私は、彼女に抑えられても身動きできなくなる。しかも、運動不足もここにきわまれり。はてどうするか。
蹴ってでも、どうにか引っぺがすしかない。
そう思って足を振り上げた時だった。
「俺がどうしたって?」
この声には聞き覚えがあった。
「アキ……ちゃん?」
「どーした、フユ。俺が来たばっかりで、帰るのかよ。それにナツは?」
「あ、ナツちゃんは仕事で来れないって。私は……」
ちらりと彼女たちを見る。彼女はバツが悪そうな顔をしていた。
「……ナツこねえんなら意味無いか。フユも帰るんだろ。先生に挨拶してくるからちょっくら待ってろ」
「いいの? アキちゃん」
「事実を言って何が悪い」
くしゃ、と大きな手でアキちゃんは私の頭をなでる。
そして、先生の方へ向かっていった。
アキちゃんは、男前で性格も良くて、スポーツ万能成績良好。絵に描いたような女子たちの憧れの的だった。
だから、美人で成績優秀のナツちゃんと一緒にいても、女子たちは陰口しか言わなかったのだ。それに私が入ったものだから、私はお邪魔虫扱いで……守ってくれるのはナツちゃんとアキちゃんしかいなかった。
そして、友人づきあいは今でも続いている。
それは、私とナツちゃんがアキちゃんの秘密を知っているからだ。
鞄をぎゅっと抱え、アキちゃんを待つ。
長い長い時間。
飲み会と言う喧騒の中にいるのに、どうしてこんなにも音が聞こえないのかも不思議だった。
「んじゃ、帰るぞー、フユ」
音が戻る。
気まずい顔をして私を見ている彼女を、ざまあみろと思った。そしてそんな自分を浅ましいと思ったのも事実だ。
冬の空は寒い。
いい加減辞めようと思うダッフルコートとマフラーに首まで沈めながら、私とアキちゃんは繁華街のはずれを歩いていた。
「ナツもこないんなら、つまんないな。こりゃ」
「……せっかくの同窓会なのに?」
「あー、別に同窓会なんて意味無いだろ。先生に会えれば俺は十分。あとはお前とナツで抜け出す予定だった。ナツにも言っておいたのによ」
私にはなかったのは、意図したものだったのだろうか? 確かに忙しくて電話もメールも最近見ていなかったけど。
「どっかで飲みなおすか。っと、フユは駄目か。どーすっかな」
「いいよ、アキちゃん。普通に昼間に皆で遊ぼうよ」
「つーたって、俺がつまらん……ゲーセンでも行くか」
「あ、なら行く」
最近私が好きなシューティングがあるんだ。それをアキちゃんは良く知っている。アキちゃんは本当に人に気を使うのが上手い。
ほたほたと、道を歩きながらアキちゃんはふと口を開く。
「フユ、知ってるか?」
「何? アキちゃん」
こういう時のアキちゃんは、面白い話をしてくれる。それが私は好きだった。
「会社の女の子に聞いたんだけどさ、25時の列車って知ってるか?」
「知らない」
というか、25時なんてない。
「ねえよな。でもさ、ある駅に25時を指す時計があって、その一瞬列車が通るんだが、それを見ると一つだけ願いが叶うんだそうだ」
「ふうん」
願いが叶う。
「アキちゃんは、何を願う?」
私の願いは。
「あー、なんだろうな。わかんね。フユは?」
私の願いは……。
「私は……」
「なんだよ」
子供のように嬉しそうに私の顔を覗き込む。きっとアキちゃんはたわいも無い事を希望しているんだろう。イラストレーターとして大成しますようにとか。
でも、私の願いは……。
「あのね……」
「うん?」
「私の願いは……」
そこで、アキちゃんの携帯が鳴る。嫌な予感。少しだけ幸せなこの時間をつぶされそうな予感。
「ああ……うん、フユもいる。ああ、わかった」
簡単な応対で済まし、アキちゃんは携帯を胸ポケットにしまった。
「セータが、来ないかって言ってるが来るか? つーか、さっきより美味いもん食えるぞ。それに久しぶりにフユに会いたいって。フォトショップで聞きたい事があるんだと」
セータさんは、アキちゃんの恋人だ。男の人だ。それがアキちゃんの秘密。私とナツちゃんしか知らない私の秘密。
「いいや、いいよ。アキちゃんは最近セータさんと会ってなかったんでしょ? 二人きりの方がいいじゃない」
「は?」
何をいってるんだ、そんな顔。
「セータはフユに会いたいといってたんだが。それに、何度も会ってるだろう?」
うん、会ってる。同じ関係の仕事の人。いや私よりももっと仕事ができる人で、私にもナツちゃんにも優しくて、とてもいい人だ。アキちゃんにぴったりだ。
「いや、ほら、私も納期迫ってるし」
「じゃ、うちでやれば?」
アキちゃんは、私が何から逃げてるかわからない。もちろんわかるはずもない。
「いや、いいよ。ナツちゃんもいないし。今日は帰る」
笑いながら私はアキちゃんの提案を拒否する。
アキちゃんの顔は、久しぶりに会えた友人に拒否されたせつなさだ。こういう所はすぐ顔に出る。
アキちゃんは優しくて、いい人で、そして、すごくすごくすごくすごく鈍感だ。
そんなアキちゃんは大好きだ。ナツちゃんも同じ事を言っていた。
だから、もう泣きそうだ。
ぽたぽたと落ちてくる涙をすすりながら、私は、
「帰る」
そういって駆け出していた。
フユ! と叫ぶ声と何度も鳴る携帯の音が聞こえたが、それはどうでもいいことだった。
うずくまる。
駅の構内でうずくまる。
もう列車は無い時間。ホームには誰もいない。
駅員さんも気づかずに帰ってしまった。
私はここで一晩過ごし、凍死するのもいいかと思った。
かちりかちりと時計の音が鳴る。
もう既に24時を過ぎて次の日だ。
雪にまみれぼんやりと、線路の先を見た。
線路の先には、まぶしい光。
気づけば、時計は25時をさしていた。
夏なのに冬の話。
次はナツで夏の話をもう一本。
|
|
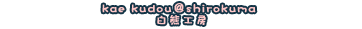
|