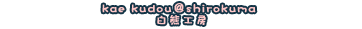うわのそら |
「帰ろう、秋葉」
そう言って、俺は秋葉の手を引く。軽い抵抗があったが、秋葉はすぐに俺に引っ張られるような形で歩いた。
俺の背中を見ているのか、そう思って振り向いてみたが、秋葉はまだ赤い夕焼けをぼんやりと見ているだけだった。夕焼けの中には、落ち葉が舞っている。どうやら秋葉はそれを目で追っているようだった。
「秋葉」
俺の声は秋葉には届きはしない。
「秋葉?」
先ほどよりも、強く手を引っ張る。
それでも秋葉は、まだ落ち葉を見ている。
「秋葉、まだ外にいたいのか?」
俺の質問に対する答えはない。
そろそろ、夕陽は赤黒い、まるで血のような色になってきていて、吹く風が冷たくなってきていた。
俺はその冷たさに身震いする。そういえば、シャツを一枚羽織ってきただけだった。
秋葉は、寒くはないのだろうか?
秋葉の服装は、髪の毛の色に似た着物一枚きり。いくら着物が俺の服装より暖かいとしても、この冷たい風にあたっていて、寒いわけがなかった。
「秋葉、寒いだろう? 帰ろう」
すでに、陽はすっかり落ちきっていて、俺と秋葉のつないでいる手がはっきりと見えるくらいでしかなかった。
「秋葉?」
反応はない。
俺はそっと目を閉じて、思い出してはいけない過去を目に浮かべた。
そう言うと、秋葉は多分「兄さん、私はもう子供じゃないんですよ。寒い暑いくらい自分で解ります。どうぞ自分のことだけ心配してください。兄さんのほうが、身体が弱いんですから」と、真っ赤な顔をして怒るんだろう。
それは、懐かしい過去。思い出してはいけない過去。今、俺の目の前にいるのは、この秋葉なのだから。そして過去の秋葉も、今の秋葉も変わらずに、俺の大事な秋葉なのだから。
「なあ、秋葉」
困ったような、少し呆れてしまったような声を俺は出す。
「俺は寒いんだ。それに秋葉、お前、腹は減ってないか」
俺の手を握る秋葉の手に、微かに力がこもった様な気がした。
「秋葉?」
くいと、秋葉の手を引っ張る。すると、秋葉は先ほどみたいな抵抗もせずに、俺の後をついてくる。
かさかさ、かさかさと落ち葉が音を立てる。
陽はすっかり落ちてしまったので、勘だけを頼りに屋敷に向かう。
かさかさ、かさかさ。
音は、俺と秋葉が落ち葉を掻き分ける音。ただそれだけだ。
俺は何だかとても寂しくなって、そっと目を伏せ、落ち葉だけをずっと見ていた。
「お帰りなさいませ」
屋敷につくと、翡翠と琥珀さんが二人して並んで、俺達の帰りを待っていた。
「あらあら、秋葉様に志貴さんもこんなに冷え切って……」
いつものように、にこにこと笑っている琥珀さんのその顔に影があったような感じがするのは気のせいか。
翡翠が音もなく、俺の方と秋葉にもう一枚服を被せた。
「さあ、秋葉様。屋敷に入りましょう」
琥珀さんが、秋葉の手をいたわるように包み込んで、そして俺のほうを向き
「志貴さんには、ご飯の用意が出来てますから、翡翠ちゃんと一緒に食堂のほうへ」
「いや、俺、食欲無いから」
「いけません、志貴様」
今までずっと無口だった翡翠からの、厳しい叱責。
「そう言って、今日は何も口になされていないでしょう。せめて、夕食だけでも」
「ごめん、翡翠。でも、ひとつも食欲がないんだ」
「でも……」
「それに」
俺は、手の先の秋葉に視線を移す。
琥珀が困ったように笑って、俺と秋葉を見ていた。
秋葉はずっと俺の手を握って離そうとしない。
「秋葉」
俺は手を長い髪にうずめた。秋葉はいつもの、焦点の合わない目でどこかを見ている。ただ、手をぎゅっと握ったまま。
「だからさ、琥珀さん。あとでアレ、よろしくね」
「……わかりました」
いつもの笑顔が微かに消えて、ぽそりと呟くように琥珀さんはそう答えた。翡翠は咎めるように、俺と秋葉と琥珀さんを見ている。
「じゃ、いつものとこにいるから」
二人とも黙ったままだ。
俺は秋葉の手を引いた。
ついと、流れるように秋葉の髪が空に流れた。
「秋葉の世界は終っちゃったのかな」
壁にもたれかかっている秋葉の頬を、ついと俺はなでた。
頭の中の世界が違うと四季は言っていた。
けれども、俺はなんだか、そんな感じよりも、秋葉の世界が終わってしまった様な気がするのだ。
「終ってないのならば、いいんだけど」
いつか、あの時のように戻ってくれればいいのに。
そう願う。
願っても、秋葉はあの秋葉に戻りはしない。願ってもしょうがない。しかし願わずにはいられない。琥珀さんの、あの悲痛な笑顔を見るのはもう嫌だ。翡翠の、無表情の中に見える悲しさも。
どうして、あの時を大事にしなかったのだろう。それは思い出してはいけない過去だけれども。
いや、思い出したら苦しくなるから、思い出してはいけないだけだ。
「秋葉」
秋葉の手が、俺の指先に絡んだ。
そして。
「痛っ」
かぷり、と秋葉は俺の指先を噛む。秋葉の犬歯は、鋭くまるでケモノのような歯になっていて、容易に俺の肌を傷つけ、深紅の液体を流した。
それは秋葉は、子供のような笑顔ですする。好物を目の前にした子供のように。
俺は黙ってそれを見ている。
ふいに、口が離れ、手が俺の肩先にかかった。滑らかな肌が俺の首筋をたどり、血管を探り当て。
かぷり。
と、秋葉は俺に噛み付いた。
どくりと、血が俺から秋葉に流れていくのがよく解る。
目の前が霞み、意識が飛びそうになる。
解るのは、絡み付いている秋葉の腕と、頬にかかるさらさらとした、そしてくすぐったい髪の毛。
「秋葉」
俺は秋葉の髪を優しくなでる。
感じるのは秋葉の重みと、そして体温、血の匂いに似た甘い体臭。
そして酩酊感。
まるで、それは秋葉を抱いた時よりも、深く交わっているような気がした。
意識が白く飛びそうになるとき、遠くで秋葉が泣いていて。
「ごめんなさい、兄さん」
そして秋葉は走り去っていく。
謝らなくてもいいのに。
そう言いたいのだけど、俺の口はどうしても動かなかった。手は石のようだった。追いかけようにも足も動かなかった。
「それでも」
俺は、身体にかかる重みを、自らの腕で確かめる。
このまま、俺の腕の中にいてくれれば、ずっと俺だけを見ていてくれればいい。
そう、思った。
前に作った月姫本から。
秋葉ED補完。
完売したのでこちらに移しました。
|
|
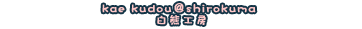
|