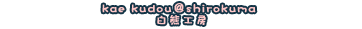あなたへの月 |
きっと、それはよくある話だ。
私が彼女を見たのがいつだったのか、それはもう覚えてはいない。
ただ、目に映った瞬間、何か強烈なものを感じたのは覚えている。
金の髪、紅い瞳。肌は抜けるように白く。いや、そんな陳腐な表現はやめておこう。そんな言葉では、私の感情を表現できやしないのだから。
ただ、彼女をどうにかしたいとは思った。
それだけだ。
ゆっくりと思い出す。
彼女の冷ややかな瞳を。
私は唇を微かにつりあげる。
「どうした? ロア・バルダムヨォン」
神父の服を着た同僚が、私に問い掛ける。
「何かいいことがあったようだな」
そうだ、確かにいいことはあった。
「いいことはあったよ」
私は、珍しくその同僚の肩に手をかけ、心の底から微笑んだ。
「私の研究の打開策がね」
同僚は、私の研究内容を知らない。いいや、この男に言ってもわかりやしないだろう。
肉体的にも、魔術的にも、ポテンシャルが高いあの女。
「それは良かった」
同僚も笑う。
真祖の姫君の力をのっとればいい。
そう、それだけ。
「なんとも簡単なことだ」
私は笑う。
楽しいのか嬉しいのかわからない。ただ、笑った。
からん、と音をたてて、大理石の床の上を何かが転がっていた。
何かはわからない。
薄暗い、ブリュンスタッド城には、一条の光が差し込んでいて、そこで転がった何かが止まり、光に反射しきらめいた。
黄色い光にきらめく、一瞬の赤い光は、姫君のアクセサリーのようだった。
それは、もう一度きらめいた。
「嘘……」
真祖の姫君は、口の端に流れた、一筋の血を手でぬぐった。
いつもの、悠然とした態度ではない、あせりの表情が見える。
一族を、いつも冷ややかに見据える紅い瞳は、驚愕のため一杯に見開かれ、ひらめくだけで人をも殺すその指先は、小刻みに震えていた。
かつん。
姫君は、後ろに下がる。ハイヒールのかかとの音が、床に反射する。
私の首筋には、二つの穴が開いている。
ぬぐうと、指先に赤い血がついた。私の血と、姫君の血。それがまざりあい。
そして、どうなるのだろう。
死して生きるものになるのか。それとも、彼女の下僕と成り果てるのか。
結果が見えないことはせず、結果が見えることばかりをしてきていた。
「しかし、それもいいだろう」
見えない。何もわからない。
それもいいだろう。
姫君は、白い顔をさらに白くし、ひたすら「嘘」と呟き続ける。
私は、首筋を押さえたまま、それをじっと見つめていた。
「嘘よ。嘘。嘘だわ」
顔を振るたびに、美しい金髪がはためいた。時折それが、光にあたり、何か宝石のようにきらめいた。
「どうして」
「姫君、あなたに血を吸われたかったから」
ひたすら自問自答を繰り返す姫君に、私は答えを与える。
「何故!」
金髪がふわりと舞い、紅い瞳が私を射抜いた。
「先ほど答えましたが、姫君」
「違う! 何故吸われた」
「あなたの眷属になりたかったからだ」
その回答に満足しなかったのか。姫君はキッと私をにらみつけた。
「私はそんなものは欲しくはない」
「しかし、私はここにいる」
一歩、姫君に近づき、私は指先についた血を、彼女の唇に塗りつけた。
いまいましげに、姫君はそれを手の甲でぬぐう。
「私はいらない」
「そうですか、でもそれは無理な相談だ」
「去ね」
「嫌だ」
彼女の指先が、私の首筋をかすめ、過ぎ去っていった。私が見切ったわけではない。本調子の彼女ならば、きっと私の首をかき切っていただろう。
喉元を抑え、姫君は明らかに苦しそうな顔をしていた。ぜぇぜぇと、漏れるような息の音がする。
「あ、ああ、あああああ」
腹部を抑え、姫君は喘ぎとも怨嗟ともつかない声を、喉の奥から搾り出すように上げた。
私の中で、何かが変わっていくような感じがする。
それと同じように、姫君も変わっていくのだろう。
私は、城を後にする。
身体にははっきりと変化が訪れ、私は死徒となっていた。彼女の影響は、微かに。
彼女が存在しているとわかるだけのつながり。
そして、姫君も何か変わっていったことだけがわかった。
私は、彼女に殺される。
何度も何度も。
そして、彼女に深い傷を負わせ、また転生の道に入る。
何度身体を変えたかはわからない。
はて、と思う。
私はどうして何度も生きているのか。
いや、それが目的だった。何度も生き、長く生き不老不死になるために、彼女に血を吸われたのだ。
しかし、これは不老不死といえるのか。
私の昔の身体はとうに滅び、精神は幾多も交じり合い。
しかし、私は動いている。
さて、本当にそれは生きているといえるのか。
鎖をちぎり、牢屋から這い出、私はかの姫君を探しに出る。
今の身体は使いやすく、よろしい。
姫君は私を殺しに来るはずだ。
美しく愛しい、私の姫君。
さあ、殺しあいましょう。
そういわんばかりに、私と姫君は殺しあう。
私と、彼女の闘いなのに。
どうして、邪魔者がいるのだろう。
まず、そちらを殺さねば。
眼鏡をかけた少年。手にはナイフが一本きり。それでは、私も姫君も殺せやしないだろう。
すでに、彼の息は上がり、身体には多数の傷が刻まれている。
「志貴」
姫君が、その少年を呼ぶ。
何度も何度も。
そのたびに私の心は、何かで膨れ上がる。
それが何かはわからない。
不安、後悔、憎悪。そんな負の情念。
しかし、それを何故そ奴に抱かなければならないのか。
「まずは、お前から殺してやろう」
心臓を握り締めればそれで終わりだ。
なんとも、人とは弱いものか。
「いいや、その言葉をそっくり返すぜ」
少年が眼鏡を外す。
一瞬、その瞳が赤く、そして猫のようになったのは気のせいか。
何かを捕らえられたかのような。
私と彼女と少年は、コンクリートに囲まれた建物を走り回る。少年のナイフは的確で、私の急所を何個も奪っていった。
しかし。
「殺すならば、殺せ。しかし、私は何度も転生する」
少年は死に、そして姫君と私だけの闘いが始まるだけだ。
「いいや」
少年は、私ではなく。
「教えてやる。これがモノを殺す、と言うことだ」
コンクリートの床にナイフを突き立てた。
カーンと、音がする。
まるで、姫君が私の血を吸った時のような、破滅の音。
あの時は、姫君の破滅の音だった。
そして、これは。
私の破滅の音だ。
硬質な音と、あの時の音と、転がる紅いアクセサリーと、そして光の筋。赤い血が目の前に霞み、そして暗くなった。
姫君の顔が見れないものかと、私は目を見開き、そして嬉しいような悲しいような、そんな複雑な顔をした姫君の顔を見て。
私の意識はそこで途切れた。
前に作った月姫本から。
ロアの切ない恋話というと御幣がありますが、そんな話。
完売したのでこちらに移しました。
|
|
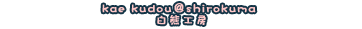
|