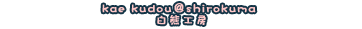冬の花火 |
私はきっとその時、彼を哀れの目で見ていたのだろう。
聞いたのは、幾度4日目を繰返した時だったろうか。彼の本名、彼の由来、彼の境遇。彼の過去。再度4日を繰返しても忘れるには程遠く、それは私の脳裏にこびりついていた。
その話はたった一度。お互いその話はもう出さず、どんな会話の際にも現れることはない。
それでも身体の端々を失い、その身は人々の勝手な思いによって山に縛り付けられてたという話は私の記憶から去ることは無く、私は何度も彼の姿をその目で確かめているようなった。
目。縫い付けられてはいない、どちらも何度もまばたきを繰返す。口は饒舌で、時折殴り飛ばしたりもしたが、軽口を叩くほどには元気だ。身体をひねり手を握り締め、身の軽い少年のように何度も飛び跳ね、足は大地を確かめる。どこにも縛り付けられてはいない。どこにも行けないなんてことはない。そうして私は安心する。
気づかれないように、彼を少しだけしっかりと見る毎日。それは愛情のようなものだろうか。そう、多分子犬を、子供を遠くで見守るようなもの。見て確認して安心する。
ただ毎日見ているうちに、少しだけ違和感が出てくるのだ。
はて。
少しだけ動作に無駄が多い。
髪を書き上げる際には、まぶたをすこし押し気味に、すっと誰にも気づかれないように上に持ち上げる。得物を持つときに指をそらし、しっかりと当て確かめている。何度も飛び跳ねたときに足の指はしっかりと大地に着くように。
そうだ、彼は自分の身体があることを確かめている。
過去に失われてしまった身体。サーヴァントを倒し聖杯戦争に勝利した際には、また戻ってしまうであろう身体。くるくると廻り飛び跳ね、そして世界を見渡せるその身体を彼は確かめている。
私の目標は勝利だ。しかし、少しだけ勝利したく無くなった。少しだけだ。少しだけ。それは感傷。子犬がいつか成犬になり、離れてしまうそれだけの感傷。首を振って私は彼を伴い、既に何度目か分からぬ戦いに赴いた。
何度も何度も戦って毎日は変わらず、夜に戦い朝に眠る。イレギュラーなことは戦うサーヴァントが違うこと。通る道が違うこと。死にいく過程が違うこと。段々戦いにも飽きつつそれでも闘志を忘れずに、私たちは夜を往く。
昼には人で溢れているであろう街にも人影は少なく、ビルはただ更に濃い影を夜に落としている。
空は、星が見えないほどに擬い物の光が彩っているが、それも夜を往く私たちには届かない。
ビルの影を二人、闇のように歩く。
「マスター。もうちょっと違う道通んね?」
「これが一番効率がいい。わめくな」
「効率効率ってさー、もうちょっと人生彩りもっても良くね?」
「うるさい、黙っていろ」
ぴしゃりとうるさいサーヴァントの口を封じる。
えーと彼は文句をぶつくさ。それを耳から耳へ通りすがらせながら、私は目の端で彼が自分の身体を確認するのを、そっと見て安心している。そんな毎日だ。
ここまで同じような毎日だと不安になってくる。いくら同じ4日間を繰返すとはいえ、こうまで毎日変わらないものか?
「そりゃー、決まったように同じ道歩くのも安心するかもしんないけどさー」
アヴェンジャーは、私の心を見透かしたようにそう文句をたれる。口うるさいが、その言葉に何となく安堵する。一度引っぱたいて、さらに闇に紛れよう。
と、ふと。
大きい音と、それに遅れて目の端に光が映った。
すわ雷か。しかし雨も無くその兆候も見られない。
再度大砲のような音。
そして振ってくる光の奔流。
「お、花火だ」
花火。
その言葉に私は振り向く。花のように大きな色とりどりの火。シャワーのような青白い滝が落ち、そして消えた。光は私たちが立っている深い闇の中にも届き、私たちを赤に青に黄色に浮かび上がらせる。
「綺麗だねえ」
まぶしそうにアヴェンジャーはそう笑う。
「お、マスター? 花火見たことない花火? こんな時期に珍しいけれど」
はしゃぐ声。そしてアヴェンジャーは、花火は夏の風物しだと私に告げる。
「ああ、綺麗だ」
眩しそうに左目を覆い、右目を見開きそれを目に焼き付けるようにアヴェンジャーは身じろぎ一つしないで火の花を見つめている。
空いている指は何度も自身を確かめるように握り締め開き、足の指が踊るように大地を叩いていた。
それは何分ほどであっただろうか。最初は時間がなくなるとアヴェンジャーを叱っていたものの、私もついつい花火に見入っていた。
最後に、大きい花火が一つ二つ三つ。華麗に夜空に光を灯すと、名残あるように藍色の空に吸い込まれていった。
「さあ、行くぞ」
私は、まだ空を眺めているアヴェンジャーをせかす。彼は動こうとしない。まだ目を確かめられるその夜を彩る光を待っている。
しかし、光はその間だけだ。私たちはまた闇の中に帰らねばならない。そのときには自分を確かめることも出来ないだろう。
だから。
「さあ、行くぞ」
私はアヴェンジャーの手を取った。それを私の手でぎゅっと握り締める。自分だけで確かめなくていい、そう言う意味を持って指をぎゅっと握った。
「マスター? 何? オレに惚れちゃった?」
私は答えない。
「マスター?」
からかうような声色は消え、いぶかしげなものに変わった。しかし私は答えない。ぎゅっと握り今日の目的地へ。
黙って私は走り出す。後ろからは足跡が。
「大丈夫だ。だから」
後ろから答えは無かった。ぎゅっと私の手を握り締める感触だけがあった。
夜を往き、そしてお前がいつか消えようとここにはお前がいるのだ、そんな私の想いに答えるように。
ホロウ本編だと「秋の花火」なのですが、たまの「さよなら人類」の「冬の花火は強すぎて僕らの身体は砕け散る」から話が出来上がったのでこんなタイトルに。
色気も何もありませんが、読んでいただければ幸いです。
|
|
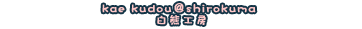
|