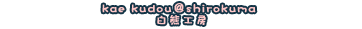evil and flowers |
目を覚ますと、そこは深い闇だった。
じっと目を凝らしていると、少しづつそれは晴れていく。しかしまだまだ昼の明るさには程遠い。
背中の柔らかい感触。シーツのぬくもり。それに私はもう一度溺れようとした。すっと目を閉じれば、心地よい眠りに落ちていけるはずだから。
目を閉じようとする前に、私は手の先にあるもう一つのぬくもりを探した。
指先を軽く動かす。
しかし、きっちりと握り締められた手のひらの重みも、肌になじむすこし湿った肌も感じない。
はっとなって、私は跳ね起きる。
目をこらし、昔の主人であり今は恋人である人の姿を捜し求める。
シーツを手でたぐる。
「よかった……」
闇に浮かび上がる彼の姿、手から伝わる彼の温もり。私はそれを探し当てて、ほっとため息をついた。
彼の手を握り締めると、温かい、しかし普通の人間の体温よりは幾分かひくいそれが伝わってきた。
温かさを確認して、私は目を閉じる。
目の前にある闇から、落ちていくような漆黒の中に落ちていくような感覚がした。
夢を見た。
一面、淡い色の花畑で、そこに私は足首だけ埋まっている。
歩くのに不自由は感じないが、黒いストッキングにさわさわと花がこすれ、こそばゆいような、歯がゆいようなな何とも変な感じがした。
一面の花。甘い花の強い匂い。
頭がくらくらする。
女の体臭の様な甘い香りをかいでいると、なんだか私自身穢れたような感じがした。
早くどこかへ行かなくちゃ。
でもどこへ?
花は地平線までずっと続いている。その上は、赤と青とそれが交じり合った変な色の紫の空が、ずっとずっと続いている。
私はこんな変な風景を見たことが無い。
――いいや。
私はおかしくてしょうがない。
変な風景を見たことが無い。のでは無く、私はあの屋敷から一歩も出たことがないと言うのに。
私はあの、でんと構えるお屋敷と、それに付随する春夏秋冬、それに裏に続く広大な庭。それしか見たことが無い。だから、これ以外の風景は全て異質なものなのに。
どうしてこれは「変だ」と感じるのだろう。
「それに」
むせかえる様な花の匂い。息が出来ないくらいの花の香り。
「どこかに行かなくちゃ」
ここにいたら息が詰まってしまう。いや、もう苦しくてしょうがない。喉に花をぎっしりと詰め込まれているようだ。
早く早くどこか遠くへ。
私は走り出す。
花びらが空に舞った。
ああ、花を踏み荒らしてはいけないのに。
花の香りにむせながら、私は走る。
この花園を抜けたい。
後ろから、何か邪悪なものがやってきて、私の花を狙っているから。
花?
この花園の花は、その邪悪なもののだけど。
私の花は?
「あ」
ふと気づくと、手に花を持っていた。
ここの、奇妙な花達ではなく、青空の下が似合う、黄色くてまるで太陽の権現みたいな。
ひまわり。
「姉さん」
私は、ふとそんなことを口走っていた。
「助けて、姉さん」
でも、もう姉さんはいない。
私の為に、姉さんは死んでしまった。
「姉さん」
私は涙を拭きながら、花園を走り続ける。
目の前に、ひまわり畑があって、そこに行けば姉さんに会える。
後ろからは、何か邪悪なものが迫ってきているけれども、そこに行けば私は守ってもらえる。
「だけど」
姉さんは、もういない。
夢なのに、いや夢だからこそ姉さんに守ってもらえる、そう思っている自分があさましい。
何度ぬぐっても、涙は溢れてくる。
「姉さん」
ごめんなさい。
好きだった人も、命も、全て私が取ってしまった。
姉さんは、それでもいいと言うだろう。
私はそれをわかっている。
「なんて、ずるい」
何をしても、何がおこっても、死んでも、姉さんは私を守っていてくれる。そう思っている自分があさましい。
「ごめんなさい」
だから、彼の心を手には入れたけれども、その代わり姉さんも、秋葉様も死んでしまったんだ。
私は走り続ける。
必死で花をかきわけ、花びらを撒き散らし、私は走る。
後ろから、邪悪なものは迫ってくる。
後ろは見ない。いや見れない。そうすれば、その邪悪なものは、花を奪い去っていってしまうから。
だから私は走り続ける。
あの、ひまわり畑へ。
だけど、走っても走っても、ひまわり畑は近づいてきてはくれない。
その代わり近づいてくるのは、邪悪なもの。
それは私の上に影を落とす。
振り向く。
花びらが舞って。
空と地面が、逆さまになってしまって。
赤と青と紫の中に、黄色いものが散らばった。
「ああ」
私は、邪悪なものの花園に埋まりながら、呟く。
「私だったんだ」
涙が落ちて落ちてしょうがない。
すでに、花園もひまわりも、涙でぼやけてしまった。
「ごめんなさい、姉さん」
私は顔を覆って泣き出す。
「秋葉様、そして――志貴様」
私は何も知らなかった、知ろうとしなかった。
どうして、私はおめおめと生き残っているのだろう。
「――翠、翡翠」
目の前は、闇ではなかった。
「志貴様」
「どうした、翡翠。うなされていたけれども」
「え――?」
首筋を触ってみると、汗びっしょりで、髪の毛が幾筋か張り付いていた。
「何か悪い夢でも見たのかい?」
「夢?」
わからない、覚えていない。
「とても、うなされていたけれども」
「いえ――」
覚えているのは、赤と青と奇妙な紫と、そして黄色。
それしか覚えていない。
「大丈夫?」
志貴様は、私の顔を優しく触った。
「ええ。大丈夫です」
そのまま、沈黙。
そろそろ夜も明けようというところか、空は暗い青色でその光がカーテン越しに部屋に差し込んでいた。
音は、何も無い。
ただ静かに。
私は黙ったまま、志貴様を見て、志貴様は私を見て。
「静かですね」
「ああ」
部屋の中は、私たちの生きている音しか聞こえない。
「翡翠」
志貴様は私の名前を呼ぶと、ぎゅっと私を抱きしめた。
「……」
「……」
私もそろそろと、志貴様の背中に手を回す。
他人の体温は、とても安心する。私が一人ぽっちではないようで。
ただ抱き合う。
それだけ。
「志貴様」
「何だい、翡翠?」
志貴様の表情はわからない。ただ、ひどく悲しそうな声で志貴様はそう言う。
「――」
私は、その言葉を言えない。
それを言うと、志貴様がひどく悲しむから。
でもそれを言わないと、自分がとても悲しくなってしまう。
「志貴様」
「……翡翠」
「誰も」
「誰も?」
やっぱり悲しそうな声。
私は勇気を振り絞って、その言葉を発する。
「誰も。誰もいなくなってしまいましたね」
「翡翠……」
普段なら、こうして恋人の部屋にいないで、この時間には起きて。食事の支度を始めている姉さんと、たあいない話をして、それに秋葉様が加わって。
秋葉様は、志貴様が起きてこないのに文句を言って、それでも志貴様を恋しそうに待っていて。
自分が学校へ行くぎりぎりの時間まで待っていて、それでも志貴様が帰ってこないとわかって、とても悲しそうな顔で、秋葉様は家を出て、それを姉さんと私で見送って――。
「ごめんなさい」
「翡翠が謝ることはないよ」
「だけど」
「翡翠」
「ごめんなさい、姉さん。ごめんなさい、秋葉様」
「翡翠!」
息が出来ないほどに抱きしめられて、私は安心する。
「翡翠が、謝る必要は無いから」
ぎゅっと抱きしめられて、ベッドにそっと寝かされる。
涙をぬぐわれ、その目の上に、大きな手がそっと置かれた。
「もうちょっと寝なさい、翡翠」
「でも」
「いいから」
頭をなでられて、とても安心する。
「ね」
「……はい」
「もう一度、おやすみ」
目を閉じた。
すっと立ち上がる音がする。
「行かないで」
私はその手にしがみついた。
「翡翠?」
優しそうな声。
「行かないで、そばに居てください、志貴様」
志貴様は苦笑して、うんともう一回頷くと、私の横に座った。
指と指を絡め、離れないようにぎゅっと握り締める。
「安心するかい?」
「……ええ」
頭をずっとなでいてくれて。
私はそれに溺れながら、また眠りの淵に沈みこんでいこうとする。
そこに引っかかっている、嫌なこと。
前に姉さんから、聞いたこと。
「ねえ、志貴様――」
「なんだい、翡翠?」
「お願いがあるんです」
「いいよ、言ってごらん」
「ずっと――」
「ずっと?」
「ずっと一緒にいてくれますか?」
また苦笑。
そして、握り締めている手に力がこもって。
「ああ、もちろん」
でも、志貴様も私も知っているのだ。
多分、志貴様は私を置いて、先にいってしまうだろう。
誰もいなくなったら、私はどこに行くのだろう。
私はぎゅっと目をつぶった。
目の前には、赤と青と紫。
そして邪悪なもの。
邪悪なものは、何もかもを奪っていってしまうのだろう。
前に作った月姫本から翡翠が感じている琥珀の負の感情の話。完売したのでこちらに移しました。
|
|
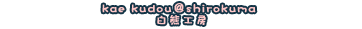
|