土蔵と剣道着と藤村大河 |
「さーて、掃除をするわよー!」
「藤村先生。そう言っても、私たちしかいません」
「……」
藤村大河は、勢いよく天に差し上げた右手を、しょぼんとしながら降ろした。左手には、雑巾バケツが下がっている。その隣には間桐桜。手にするは、はたきと箒。そして二人とも、胸にはエプロン。大河にはもちろんトラ柄、桜はさくら色のエプロンだ。
なぜ、藤村大河と間桐桜が蔵の前に大掃除のいでたちをして立っているのかは、少なくとも1時間前にさかのぼる。その話は果たして、深遠で壮大なのだが、はしょっていうと、こうなる。
「いい加減蔵の中のガラクタを掃除してくれ。しないと、食事抜き」
そんなわかりやすいムチにて、衛宮亭の主人は居候化している猫科の生き物、藤村大河に言い放ったのだ。
そんな、ひどいと、三度の飯は欠かさない、居候三杯目も勢い良くなセイバーは言うが、衛宮亭の主人は聞く耳を持たなかった。なんでも、修行する場所さえすでに、大河の私物で侵されているそうなのである。その有様は、誇張という形容詞を持たない衛宮士郎の口調からさえも、居候たちに恐怖を持って伝えられた。そして、皆口々に言うのだ。掃除しなさいと。
涙を浮かべても、かわいこぶっても駄目、掃除しなさい。姦しい女どもからの機関銃のような口激に耐えかねて、藤村大河も陥落した。しかし、誰か手伝ってという条件を持って。
たしかに、衛宮士郎から伝えられた状況からするに、そこはあまりにも悲惨な様態を呈していると思われる。多分にこの散らかし魔、藤村大河では一日どころか一ヶ月を持ってしても、土蔵のガラクタ雪崩を掃除する事は出来ないと、容易に想像できた。
「しかし、シロウ。私は今日、どうしても外せない用事が」
そろそろと手を上げて、さも申し訳そうに告げるのははセイバーで、いつも番犬ならぬ番ライオンとして、日がな一日衛宮亭に居るのに、さて珍しいと思ったら、サッカーの試合が川原であるそうなのである。これはどうにも外せない。行ってらっしゃいと住人たちは、快くセイバーを送り出した。すまなさそうにぺこぺこと、セイバーはサッカーボールを抱えて走り去っていった。
さて、赤いあくまこと遠坂凛様は、
「寝せて」
の一言だった。
どうにも、徹夜をしていたらしい。今にもちゃぶ台に墜落寸前だ。そういえば確かに発言が少なかった、と一同納得。そのまま退場頂いた。
ライダーはつれっと、バイトがありますの一言。イリヤはいやーやだーめんどくさーいと拒否し、さて残ったのは士郎と桜と……そして大河。
「俺さ、甘やかしてたら藤ねぇの為にならないと、思うんだ」
手を上げて一言。
確かにいつもならば、ここで大河がごねて、さて士郎が片付けました、というオチだろう。しかし、そうは問屋が卸さない。士郎君も学習能力があるのだ。
「ご飯作って待ってるからさ」
ここはとても甘いが。
さて、残るはこの二人、間桐桜さんと藤村大河さん。かたや掃除をする理由はまったく無く、さてもう一人は理由がありすぎるという、まったく対称的な二人である。
「わ、わたし……」
「あっりがとー、さくらちゃーん」
最後まで言わずともわかるというか、道連れを増やしたいだけなのか、おずおずとそう切り出そうとした桜に、大河は思いっきり抱きついた。桜の胸が、ぽよんと揺れる。
「さくらちゃーん、恩にきるわー。あっりがとぅー。私一人じゃ、この世が滅んだって終わんなーい」
自分の特性は、さすがによく理解しているようである。
さて、そんな昼下がり大河と桜で、土蔵の掃除は始まったのである。
もくもく。もくもく。もくもく。
もともと掃除というのは、誰かと話をしてするものではない。その為必然的に無口になる、はずなのだが。
ほこりを落として、いらない物といる物を分けて、箒をかけて、拭き掃除。その、いらない物を分けるのが異常に時間がかかっている。掃除のときについ、本を読みふけってしまう状態と同じ事が、藤村大河にも起こっていた。
そう、
「うわー懐かしい。だっこちゃん人形だ。あ、フラフープ。桜ちゃーん、みてみてー」
「藤村先生! ちゃんと掃除してください!」
「ごめんごめんー。あっ! これ懐かしいー」
こんな調子である。
いい加減桜が切れて、全て捨てます! と、叫んで少しの間だけちゃんと片付ける、そんな状態だ。桜は、こんな調子じゃ終わらないわ、とため息をついた。
桜はさくさくと、いらない物といる物を分けている。いや、分けるのはとても簡単なのだ。なにしろ大半が、誰でも分かるいらない物だらけ。ふじむらたいがとかかれた筆箱、たこやき機、顔がかいてある壷、どこからどこまでノンジャンル。よくもまあここまで集めたと、桜も感心するほどである。
手際よく分けている間に、一つ桜は古ぼけた箱を見つけた。いままでのガラクタとはどうにも違う、お菓子の箱。ガラクタのようにごっちゃになってはなく、そこに置くべきものとして置かれたもの。
なにかしら、桜は無意識にそれを開ける。
「あ……」
それは白と黒の布。開いてみると良く分かる。弓道とは似て異なるもの。それは誰もが知っている、伝説の剣道少女が身につけていた剣道着だった。
「先生」
桜はそれを大河に差し出した。
「先生、これ」
「ん、何? 桜ちゃん」
あ、と一瞬だけ大河の動きが止まった。それはとても微細なもの。普段の大河を知る者でしか分からない、しかし、普段彼女の動作を知っていれば、それは意外と思える態度だった。
それに含まれるは、郷愁、既にかすれてしまっている痛み。それは、いつもの藤村大河からは見られないものだった。
「なつ……かしい」
既に、最後の口調はいつもの藤村大河に戻っていた。にこにこと笑いながら、剣道着を広げる。
「懐かしい。こんな時期もあったのよね」
「そうですか。先生」
桜の口調はあくまでも優しい。その態度にまったく気づかなかったかのように。
「うん。懐かしい。これね、全国大会に行ってそのまま封印しちゃったの」
大河は誰が聞くともなしに、過去話を始める。
「実はね」
これは、あの時期に藤村大河の近くに居たものならば、誰でも知ってる話だ。衛宮士郎でさえも。
「昔ね、切嗣さんのこと……士郎のお義父さんの事が好きだったの」
「そう……ですか」
もちろん桜も、聞くともなしに知っていた。高校生の剣道少女の可愛らしい恋愛。それは英語の教師としての藤村大河の過去の噂話として、誰もが知っている話だった。
「で、ね。ちょうどその頃、剣道の全国大会があって」
大河は、白と黒の剣道着をぎゅっと抱きしめた。
「切嗣さんはそれまで、全然私の試合を見に来てくれなかったの。何度誘っても何度も。だからね、その時も、いつもみたいに諦め半分で言ってみたんだぁ」
懐かしいあの時を思い出して、胴着にほお擦りをする。
「そしたら、来てくれるって。嬉しかったなぁ」
「そうですよね」
桜も、それを彼の息子に重ね合わせて、想像する。それはとても嬉しいだろうな。そう思って。
「でね」
「はい」
いつの間にか、桜も身を乗り出して、その話を聞いていた。
「その時、優勝したら、切嗣さんに告白しようと思ってたの。はっきり言って、負け無しだったから絶対告白できる、そう思ってた」
「そうしたら?」
何処かそれは、アンハッピーエンドのにおいがする。それでも、桜は先を促して聞いてしまった。
「負けちゃった、一回戦で。負けちゃったの」
大河は、ぎゅっと胴着を抱きしめた。
「負けちゃったんだぁ」
笑顔で、胴着にほお擦りをして、そして目の端には涙が浮いてた。
それをぎゅっと目をつぶって、大河はかき消した。それはもうアンハッピーエンドではなくて、コメディにする為の呪文のように。
「剣道は、続けたんですか?」
場違いな桜の質問、それに大河はやっぱり笑って、
「うん、続けた。でもね、このどうしても悔しくて、竹刀と胴着をね、ここにしまい込んだの」
箱を取って、そこに胴着をしまう真似、そして竹刀を折り曲げて、そこらに放り投げる真似をした。
「そして、次の日にまっさらな胴着を着て練習してたわ。でも、竹刀を折ってたから、先生にとっても怒られた。そうそう、そこらにきっと竹刀の残骸があるわよ」
ふふ、と二人顔を見合わせて笑う。二人に共犯者のような、そんな連帯感を抱かせ、そして、どちらかか、それとも両方かもしれないのか、お腹がぐぅと鳴った。
顔を真っ赤にして、腹部を押さえそして声を上げて笑う。ひときしり笑った後、
「そういえば、先生、もう外が暗く……」
「あ、いけない。士郎にご飯抜きにされちゃう!」
慌てて二人は片付けだす。
大きな声で、ご飯だと呼ぶ声が聞こえた。まだ土蔵は半分も片付けてない。でもいいか。そう笑って二人は、はぁーいとその声に答えた。
タイトルのままの話を一本。大河でシリアスをやろうと思いましたが、ここが限界でした。
|
|
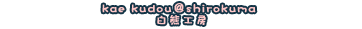
|