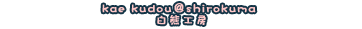架空の犬 |
バロック屋に入り、私はゆっくりと辺りを見回した。不機嫌そうにパソコンに向かっている男は、私を見るとたちまち愛想笑いをした。多分にこの男がバロック屋なのだろう。その男の背中越しに、少女が興味津々という体で覗き込んでいる。白目がちな瞳が、まるで猫を連想させる。古ぼけたソファに沈み込んでいる身体は華奢なのに、胸だけがやけに大きかった。
「いかがしました?」
バロック屋がそう聞いてくる。しかし私はバロックではない。バロックにはれっきとした証拠がある。空を見ている遠い左瞳。一般人でもすぐにそれとわかるのだ。バロック屋なら、すぐにそうと知れるだろう。バロック屋にはバロックしか入らないと聞いている。しかしバロック屋は、普通に客に相対するように私に接してくる。まるで、モデルハウスの案内嬢のような、張り付いたような笑顔で。
「バロックを買って欲しいのですが」
「それはどのような」
少女が無関心を装いながらも、しっかりとこちらの会話に耳をそばだてている。そういえば普通バロック屋では、バロックが自分のバロックを売ったり買ったりするのだそうだ。
やはりバロックに侵されていない人間は珍しいのだろうか。
「このフロッピーの中に入っています」
バロック屋のパソコンの傍らに、黒いフロッピーディスクを滑らした。何の変哲もないフロッピーディスクだ。そう、中身以外は。
「貴方の?」
あの愛想笑いのまま、バロック屋はフロッピーディスクを受け取る。以外に繊細な指をしていた。それが慣れた手つきでフロッピーディスクをパソコンに入れる。
「いいえ」
キーボードを叩くすばやい手つきを眺めながら、バロック屋と同じ愛想笑いを顔に浮かべた。
「私の友人のバロックです。そう、それにはちょっとした話があるんです」
私はそのころどこにでもいる怠け癖のついた、平凡な大学生だった。
いつだったかは覚えてはいないが、それは大学の昼休みもとうに過ぎてしまったのに授業にも出ず、授業のある部活の奴らを送り出して、部室にそなえつけてあったTVを、なにをするでもなしに眺めていたときだった。
ふいに部室のドアがノックされた。私はびっくりして飛び上がった。部活の奴ならノックなどしない。時計を見て授業はまだ終わっていないことを確認する。ゼミの教授も授業中。あまりにも授業に出ないので、一回ここに押しかけられたことがあったのだ。
では誰だろう。
部の人間の友人だろうか? うちの部はたまに部員以外の溜まり場にもなっているし。
はい。と小さく呟いてドアを開ける。
「はぁい」
立っていたのは、部員でも教授でも部員の友人でもなかった。いや、部員だとはいうのか。ただし過去の。一年前にジャーナリストになるといって、突然大学を中退した奴だ。
「珠緒?」
「そーう」
そう、奴の名前は赤城珠緒という。彼女は一年前までこの大学の経済学部に在籍していた。私は図書館学でぜんぜん専攻は違ったが、この学校で一番仲が良かったとは認めている。
スレンダーで均整の取れた身体に、小さい顔がのっている。あごのあたりでシャギーを入れた髪は鴉の濡れ羽色で、その中にある気の強そうな大きな瞳も漆黒だ。
手ごわそうな美人。それが、ほとんどの人の感想で、またその期待を裏切ることもないれっきとした変人だ。
「なにやったのアンタ。中東から強制送還されたんかい」
「うるさいわ」
軽口を叩きながら、珠緒のためにパイプ椅子を一つ引き出し、買い置きのジュースを投げて渡す。久しぶりと言いつつあたりをきょろきょろと見回している珠緒を瞳の端に映しながら、私は年代物の椅子に腰をおろした。
最初はたあいもない話だった。この前まで行ってた国のこと。最近の大学事情。そんな話ですぐに時は過ぎていった。
珠緒が日本に戻ってきたのはけっこう前のことらしい。早目に大学に顔を出したかったんだけど、という弁解を聞きつつ私はぼんやりと珠緒の顔を眺めている。
「それで、バロックがね」
「バロック?」
聞きなれない言葉だった。バロック。ばろっく。なにか不安定な感じがする言葉。
「え、あ、知らない? あんただったら知ってると思ったんだけど。私が日本に帰ってきたのもこのことでさ。最近あったあれ知らない? 放課後屋上殺人事件」
「あーと。女子高生が男の子の目玉えぐりだしたやつ?」
覚えてるも何も、新聞テレビで大々的に報道されたのだ。覚えていないほうがおかしい。しかし奇妙な事件だった。普通若者の猟奇的殺人というのは、自分を世間に誇示するために行われるのが多いのに、その事件にはそんなところが一つもなかった。自分の内的世界の完結のための事件。そんな感じだ。最近そんなニュースがちらほらと出始めている。
「そうそう。それ。今それを追っかけてるのよ。あんな事件を起こした子はねやたら強烈な内的宇宙持っていて、それがあまりにも荒唐無稽なのに圧倒的なのよ。それでバロックって言葉を誰かがつけたの」
「オタクじゃねーか。それは」
「奴らはやばいオタクよりも話を聞かないね」
肩をすくめてにやりと笑う。
「しかもすごいよ、アンタ。妄想が」
珠緒は大きな黒のショルダーバックから、赤に、黒でやたらと装飾過剰なデザインがされた十字架が描いてある手帳を取り出した。ああ、そういえばバロックっていう装飾様式があったな、と思い手元を覗き見る。マルクトという文字が書いてある。なんだっけ、セフィロトのなんか・・・。
「それで」
手帳を読み上げる。
「『私の中にはカンカクキュウが詰まっている。そのカンカクキュウは私を支配していて、もう私の人格はどこにもない。カンカクキュウは私の普段の行動もコピーしているので、私の行動を不審に思うものはどこにもいない。親兄弟も、友人も私を動かしているものが私ではないことに気づかない』」
私は、文章を読み上げる珠緒の顔を見ていた。どこも変わらない。ただ瞳が、漆黒の美しい左瞳だけが宙を浮いて・・・遠くを見ている。
「珠緒?」
「何よ、いったい」
途中で中断されたせいか、不機嫌な態度をもろに出して珠緒は言う。いつもの珠緒だ。私はほっと胸をなでおろす。しかし心の奥底では、何かがくすぶっている。なにか不安のようなものが。
「いいや、なんでも。・・・あ、ちょっとした疑問。カンカクキュウって何?」
「さあ? 世界の端末みたいなものだって言ってたけど・・・っと、わっ!」
私の後ろの壁を見て、珠緒は素っ頓狂な声を上げる。
「なに、蜘蛛でもいたの」
この女は蜘蛛が大の苦手なのだ。
「それは、やめてよ。違うって。時間。待ち合わせがあってさ」
「デート?」
「そうデート」
お互いににやりと笑って、私は珠緒の退出の支度を手伝う。あせって用意をして物を取り落とすといういつもの彼女をみつつも、なにか不安のようなものが心を押しつぶしていく。
「じゃあ、暇になったら連絡ちょうだい」
「うん。部活の皆にもよろしく言って」
珠緒あっさりとドアを閉めた。やれやれと私は首を鳴らす。ふと見ると、先ほどまで珠緒が座っていた場所に白い羽が落ちていて・・・。
「羽?」
はね。
端末みたいなものだって言っていた。 遠い左瞳。カンカクキュウ。 マルクト。 バロック。
私は心に引っかかっていたものを一つずつ思い出していく。妙な胸騒ぎ。飲み込まれていくような何か。不安。不安。不安。
私はドアを開けていた。廊下に小さくなっていく珠緒の姿を認めて叫んだ。
「今週の土曜空いている!? 飲みに行くから空けとけ!」
私の大声に、学生たちがいぶかしげな目つきで私を見る。だが珠緒は満面の笑みで身体で大きくまるを作った。三日後に土曜日は来る。なんだか大きな安心を貰ったようで、私はほっとため息をついた。
珠緒が死んだのはその日の夜だったそうだ。死因は急性心不全。つまり死因は不明ってことか。家族は過労だと思っているらしい そして私は形見わけに一枚のフロッピーディスクを貰った。なにも変哲もないフロッピーディスク。しかし、私は「架空の犬」と書かれた一行を見ただけでそのフロッピーを閉じた。
。私は確信している。
珠緒はカンカクキュウに飲み込まれたのだ。では本当の珠緒はどこに行ったのだろう。
「今はバロックという言葉も一般的ですし」
「そうですね」
バロック屋は少しだけ神妙な顔をしている。しかし目はディスプレイに走らせたままだ。
後ろにいる少女が何か口を開きかける。しかしそれはけたたましい警報にかき消された。異形殺戮部隊の警報。異形という人ではない物の存在は、バロックが一般的になってから、どこからともなく現れはじめた。しかし、その前にバロックという非日常に慣らされた一般人にとって、無感動に受け入れられていた。
何かが変わっていく。少しずつ不気味な方向へ。それは少しずつであるがゆえに、人々に違和感を感じさせないのだろうか。
「すごいですね」
警報はどんどん遠ざかっていく。
「ええ、最近は多いですね」
そうだ、日に何回もある。もう数えるのも止めてしまった。この音など、私も含めて大衆は消防車と同じくらいにしか考えてないだろう。異形殺戮部隊の警報がしたら、車は速やかに端によけて・・・。
「ねえ、バロック屋さん。昔とかなり変わってしまいましたね」
「そうですね」
おざなりな返事だ。でも私は語る。何が私を突き動かしたかはわからない。
「でもきっと何も変わってないんですよ。ただ我々の持つ何か、そう歪みというものが、表面に出てきて、それまでおおっぴらに言えなかったものが、バロックという名前を借りて出てきたんだと思うんです。きっと、最初から何も変わってないんですよ。ええきっと」
バロック本「CANIS FANTASTICS」から。
|
|
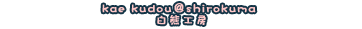
|