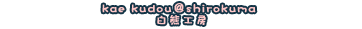森林学者 |
私が彼に出会ったのは、世界がとうに歪んでしまって、それが真なのか擬なのか、人々も区別がつかなくなってきた、そんな頃だ。
世界が歪む前、私はただの森林学者という肩書きを持っていた。ある大学の研究室で過ごす、穏やかだが刺激のない日々。ただそれだけだった。
何も変わらない安定した人生。それでいいのかと思いながらも、毎日を過ごしていると、世界は私たちが気づかないうちにだんだんと歪んでいく。それもだんだん日常に埋没していったある日、あの大熱波がおきた。
親兄弟は見つからなかった。友人はどこかへ行ってしまった。知人は歪んでしまい、異形になる者もいた。
学校、政府。我々が大熱波前に頼りにしていた機関は機能せず、この荒廃した世界でかろうじて秩序を保っていたのは、マルクトという奇妙な宗教団体だけだった。
天使に擬するこの奇妙な宗教団体は、大熱波前からあったが、かなり世間は腫れ物に触るような扱いをしてきた。
そして大熱波後も、歪んだ人々はあの大熱波がこの教団のせいだと噂する。誰もがそう思っている。しかしこの教団に文句をいう者はあまりいない。
おおっぴらに言った者は皆、神経塔というあの歪んだ塔につれさられて、帰ってこなかったというのだから。
そして私はというと、その委託で森林調査などというものをやっている。歪んでしまっても変わらない日々。ああ、これでいいのだ。これが幸せなのだ。そう思い始めたころだった。
いつもと変わらない、森で過ごす日々。森へと出かけようとしたとき、私はいつもとは違うものに出会った。
マルクトの、もうぼろぼろになってしまったポスターが貼ってある壁。そこには見たこともない青年が立っていた。外見はどこにでもいる平凡な青年だ。しかし、その瞳はうつろでぼんやりとあの神経塔を見ている。
大熱波がおきてから、あの塔を見るものなどめったにいない。見るのはマルクト教団の者と、あれに関係あるバロックを持つものだけだ。ここらへんにたむろする、教団員やバロックの顔は大抵私は知っている。
「どうしたんだい」
気になった。
「あれを見てはいけないよ。呪われてしまう」
こんなことをマルクト教団の奴らに聞かれたら、一発でお縄だ。私は何を思っているのか。
青年は振り向いた。幼い顔立ち。うつろな瞳。ずるずるのコートを着ていて、袖の先には・・・、マルクトのマークがあった。
しかし、私の発言にも青年は頓着しない。私の顔をそのうつろな目で見つめて、そしてひどくできそこないの笑顔を作った。何度か首を振って、口をパクパクあける。
「口がきけないのかい?」
私の問いに青年は、またできそこないの笑顔を作った。
「大変だったんだね」 きっとこの子は、大熱波のせいで口が聞けなくなってしまったんだろう。羽もないから、とても下っ端のマルクト教団員なのだろう。可愛そうに。
「そうだね、大変だね。あれ以来」
青年は首をかしげている。言葉がないせいで、それが何を意味するのかはわからない。
「でも、まあ生きていけるし。・・・まだ教団の方はなんだかごたごたがあるらしいし、あれは教団のせいだと噂されているけどね。でも私たち庶民には、きっとたいして変わりないんだろうね。起きて食べて寝て。それの繰り返し。世界を、運命を変えるのは選ばれた一握りの人たちとか、雲の上の人たちで、私たちは一生それに降りまわされて生きていくだけさ。私たちの一生は、きっと砂の一粒にしかすぎないんだよ」
なぜそんなことを言い出したのかは、わからなかった。青年のぼんやりした顔が、何事をも言いやすかったのかもしれないし、神経塔の毒気にあてられたのかもしれない。
気がつくと青年が、私の袖をぎゅっと握り締めていた。
言葉の出ない口が、かすかに動く。
ごめんなさい。と。
青年は去っていった。そう、あの神経塔に。あの日から、何度も何度もあの青年を見かけるが、どうも私を覚えていないようだ。
あの日から私は仕事が手につかない。
いつもいつも、あの青年を待っている。
私を覚えているあの青年を。
首の長い男も、角の生えた女も、袋に入った少女も消えてしまった。神経塔は今や歓喜の声を鳴らしている。
でも私は待ち続けるのだ。あの青年を。
バロック本「CANIS FANTASTICS」から。
私の社会に対するイメージも、こんなのなのかもしれない。
|
|
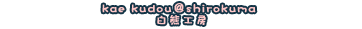
|