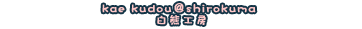星の灯火 |
祖母は時折、何かを懐から取り出しては、眺めていた。親指と人差し指ではさむようにもてる、小さな小さなガラス瓶。祖母は、揺り椅子にもたれては、目を細めて、その中にあるものをいとおしむようにじっと眺めるのだ。
ガラス瓶は光っていた。中にあるのは小さな光る青い小石のようなもの。それはロウソクの光よりもずっとはかなげにゆらゆらと光る。それを眺める祖母の姿は、子供心にもどこか近寄ってはいけないようで、僕は祖母がそれを見ているのを、ものかげからじっと見ていた。
「ねえ」
ある日僕は問うた。それには何が入ってるのかと。それは子供の頃の僕の、精一杯の勇気を振り絞っての問いだったが、祖母は何も気にせずやんわりと笑い、揺り椅子を揺らして言った。
「これはね、星が入っているの」
「星?」
「そう、星」
そんなものが入っているとは思いもよらなかった。僕の勝手に出した答えでは、それは発光する石(なんとも陳腐な回答だ)だった。考えても見ろ、もう世の中は大陸中に蒸気機関車が巡り、夜にはガス灯があたりを明るくともしている。そんな時代に、星。
しかしはんなりと笑う祖母が嘘をついてるとも思えなかった。
僕の頭はぐるぐると回った。星が(本当だとしてもだ)、祖母の手元で光っているのだ。困惑しないはずがない。いろいろな考えがぐるぐると回っている頭で、僕はまた祖母に問いかけた。
「星、は夜空にあるはずじゃない」
「ええ、そうよ」
「じゃあ、なんでお祖母ちゃんが星なんて持ってるのさ」
僕は多分、夜空から落ちてきた星を拾ったのよ、と祖母が答えるだろうと思っていた。小さい頃からおとぎ話、童話を聞いて育ったが、それくらいしか思いつかなかった。しかし、祖母の口から出た答えは思いもよらぬことだった。
「それはね、昔お祖母ちゃんは、星を撒くお仕事をしていたからよ」
「うそだあ」
思わず口をついてそんな言葉が出た。あまりにも突拍子もない答えだったからだ。
「嘘じゃないわ」
祖母は私を抱え上げ、ひざに乗せた。椅子がゆれ祖母の銀髪の後れ毛が揺れた。まつげを伏せ、祖母は語りだす。
「お祖母ちゃんの故郷はね、朝落ちてきた星を拾ってお空に撒く仕事をしていたの。村中でね。女たちは光を失って落ちてきた星を拾い集め、工場で光を取り戻すの。男たちは飛行機に乗って夜空一面に星を撒くの。そんなお仕事」
「飛行機!」
僕は胸が高鳴った。飛行機! 最近どこぞの国の兄弟が飛行機を完成させたというニュースが話題をさらっていた。男の子たちは、大空を飛ぶ機械に胸をときめかせてた時代だ。その飛行機で星を撒くのだ。心が躍らないわけはない。
「それでね」
祖母の話は続く。
「昔はガス灯の変わりに、星を燈していたの。空に撒く星を少し増やしてね」
そう、こんなふうに。祖母はあの小瓶をきらめかせる。
「今はガス灯になっちゃったけど」
「じゃあ、どうしてお祖母ちゃんは星を拾う村にいないの?」
そのとき祖母の顔は少しだけ強張っていただろう。子供だった頃の僕にはわからなかったが。僕を抱く手がかすかに震えていた。祖母は僕を抱き寄せ、瞳を覗き込んだ。空のにおいが僕の鼻を通っていった。祖母のにおいだ。
「それはね、お祖母ちゃんは少し冒険好きな女の子だったの。それで男たちの乗る飛行機に隠れて、そしていつのまにかここにいたの」
「そうなの?」
「そうよ」
祖母はかすかに笑った。その笑みが何を意味するかは、小さい僕はわかっていなかった。ただ子供の好奇心で祖母を質問攻めにしたのだ。空を飛んだときはどうだったか。怖かったか、楽しかったか。それにいちいち祖母は答えてくれた。
質問にも飽きて、僕はやわらかい祖母のひざの上で小瓶をもてあそんでいた。
「ねえお祖母ちゃん。これちょうだいよ」
子供の残酷な無邪気さで、僕は祖母におねだりをした。いつも僕のわがままを笑って聞いてくれていた祖母だ。その願いも簡単に通ると思っていた。
美しい動作で、僕の手のひらから小瓶を取り上げ、懐にしまった。
「でもね、お祖母ちゃんが死んだらあげる。お母さんにもお父さんにも見つからずに、そっとお祖母ちゃんのここからとりなさい。でもそれまではおばあちゃんのものよ」
僕があまりにも残念そうな顔をしたせいだろうか、苦笑しながら祖母は懐を軽くたたいた。
「じゃあ、いらない」
僕は祖母のひざから飛び降りる。
「お祖母ちゃんがしんじゃうならいらない。いらないから、飛行機の話をしてよ」
これは本心だった。
そうして僕は飛行機と、空に星を撒く村の話を聞いて育った。誰にも言わなかった。これは僕だけの星なのだから。
祖母は死に、僕は大きくなりそしていつのまにか飛行機乗りになっていた。しかし、空には暗雲が立ち込めていて、空に星を撒く優雅な雰囲気なぞひとつもなかった。飛行機乗りは、殺し合いのために空を飛ぶしかなくなっている。
僕は祖母の小瓶を胸にぶら下げ黒い空を飛んでいる。いつかあの、星を撒く村にたどり着けることを夢見ながら。
卒業制作で、空に星を撒く人々のムービーを作りました。それから派生した物語です。編はほんとのんきな話ですが。
まだ数本話があるので、お付き合いしていただければ幸いです。
|
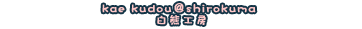
| |
|
|